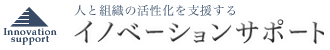直近6ヶ月分を公開しています。表題をクリックするとより詳細な内容が、アイコンをクリックするとPDFファイルで詳細がご覧になれます。
| ≪連載 第26回≫待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 | 2026年01月 Vol.281 |
|
|---|---|---|
| ≪連載 第25回≫待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 | 2025年12月 Vol.280 |
|
| ≪連載 第24回≫待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 | 2025年11月 Vol.279 |
|
| ≪連載 第23回≫待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 | 2025年10月 Vol.278 |
|
| ≪連載 第22回≫待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 | 2025年9月 Vol.277 |
|
| ≪連載 第21回≫待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 | 2025年8月 Vol.276 |
|
≪連載 第26回≫ 待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 Vol.281
Chapter 3 DX時代の開発手法 15.プロジェクトの評価 1つの案件が終わったら、プロジェクトメンバーで振り返り、DX計画書の内容通りに進んでいるか、費用対効果などを確認します。次に進むためにも必須の作業です。 1)改善の定量/定性効果の確認 作成したDX計画書で費用対効果を見積もりましたので、実際にどのような効果があったのか整理します。この結果を決裁者に早く上げることで、次のプロジェクトへの投資と、DXに対する期待値を獲得できます。例えば、デジタライゼーションの目的がコスト削減となっていれば、成果は見積もり易いですが、無駄にコストをかけ過ぎなかったか、想定通り工数を削減できたかなどまで、改めて整理しましょう。・・・・・
- <コラム>スポットワーカー活用のポイント!
- ◆人手不足が深刻になる中、人手足対策の切り札として、最近、注目を集めている働き方が2種類ある。一つは「ギガワーク」で、ギグワーカーは業務委託契約(個人事業主として)で企業に属さず仕事を受ける働き方。もう一つは、「スポットワーク(スキマバイト)」で、スポットワーカーは雇用契約(アルバイトとして)を結び、企業から指揮命令を受けて働く働き方です。主な違いは契約形態にあります。そうした中、1日に数時間といったスキマ時間に働く「スポットワーカー」の活用が進み、独自の仕組みで働き手を囲いこみ、・・・・・
- <today's>ロート、新卒の書類選考廃止 AIの普及で内容横並び 人事担当者が15分対話
- ◆ロート製薬は15日、2027年4月入社の新卒採用から、エントリーシートによる書類選考を廃止すると発表した。代わりに人事担当者との15分間の対話による選考を導入する。原則対面で実施し、その後に複数回の面接やグループワークを経て内定を出す。生成AI(人工知能)の普及で応募書類の内容が均質化しており、対話を通じて学生一人ひとりの個性や価値観を把握する。導入した「Entry Meet(エントリーミート)採用」は全国8カ所の会場で、15分間の対話で実施する。応募者は採用ページから・・・・・・・
- <today's>新成人 昨年と並び109万人 2番目の少なさ 午年生まれは940万人
- ◆総務省が31日公表した2026年1月1日時点の人口推計によると、07年生まれの新成人(18歳)は109万人で、25年と並んだ。統計がある1968年以来最少だった24年の106万人に次ぎ2番目に少なく、少子化の流れが続いている。年男・年女に当たる午(うま)年生まれは940万人で、十二支別にみると最も少ない。総人口に占める新成人の割合は0.89%で、前年より0.01ポイント増えた。男女別では男性56万人、女性53万人。・・・・・
≪連載 第25回≫ 待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 Vol.280
Chapter 3 DX時代の開発手法 13.ユーザーテストの注意点 開発して利用が可能になるとテストをおこないますが、その際の注意点を述べたいと思います。 1)現場のユーザーとテストを行う 機能が完成したら、不具合がないか、意図したように動き、ユーザーが使い易いものになっているかの確認は重要です。ポイントは、現場でユーザーに使ってもらうこと。まず、これまでのビジネスプロセスに比べて使い勝手がどうかを確認します。エンジニアには、色々なパターンがある業務プロセスのすべてを把握することはできません。つまり、エンジニアに・・・・・
- <コラム>ジョブ型社員の解雇は・・・!
- ◆近年、人材の流動化、中途採用の活発化に伴いジョブ型雇用が多く見られるようになってきた。従来は、人に仕事を割り当てるメンバーシップ型雇用が中心だったが、最近では、仕事に人を割り当てるジョブ型雇用や、その折衷型の雇用が増えてきている。最近増えてきた職務限定型のジョブ型雇用労働者の解雇につき、東京高裁が専門職男性の解雇を容認する判決を出し確定した。事案は、三菱UFJ銀行に約11年間、円金利情報など日本経済を分析する専門職として勤務した男性が、業務のグループ企業への移管に伴い、・・・・・
- <today's>20代で課長・年収1000万円も 西部ガス 来春から新人事制度
- ◆西部ガスは年功序列型の人事制度を見直し、個人の業務成果に応じて評価する役割等級制度を2026年4月から導入すると発表した。制度上は20代で課長に昇格でき、年収も1000万円を超える。社員の能力を給与や役職に反映しやすくすることでモチベーションを高め、生産性の向上を目指す。 これまで管理職への昇格は40歳前後だったが、新制度では20代でも昇格できるようにする。同社では課長以上を管理職とすると定めており、課長に昇格すると年収は賞与込みで1000万円超になるという。・・・・・・・
- <today's>建設資材の配送・在庫管理 佐川急便が一括代行 工期短縮を後押し
- ◆佐川急便を傘下に持つSGホールディングス(HD) は、建設資材の配送と在庫管理の一括代行サービスを始める。建設会社と組んで各メーカーの専用倉庫に集約し、必要に応じて現場に運ぶ仕組みをつくる。資材がバラバラに届くことで作業の効率が悪化していた。SGDHは宅配便のノウハウを建設業界に導入し、工期短縮につなげる。≪中略≫第1弾として、空調設備工事で国内最大手の新菱冷熱工業(東京。新宿)から資材輸送を受注した。新菱冷熱が資材メーカーに発注した換気扇や送風機と言った製品を、SGHDの倉庫に収めてもらう。・・・・・
≪連載 第24回≫ 待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 Vol.279
Chapter 3 DX時代の開発手法 11.アジャイル開発の進め方 外部環境に左右されないビジネスの構築がDX化、環境変化に応じてスピーディ開発を行うことは言を待ちません。これを支えるのが「アジャイル」という手法です。1)アジャイル開発が適しているわけ この開発手法の優れている点は、機能単位で素早くリリースし、ユーザーの反応を確認しながら改善できる点です。また、業務の一部からリリースすることで、ユーザビリティだけでなく、ビジネスニーズにもフレキシブルに対応で来ます。2020年から始まった新型コロナ禍の影響もあり、経営は環境変化対応がさらに求められ、具体的にはテレワークへの対応など業務システムに対する要望も一層強くなり、ビジネス自体のスピードアップが求められています。こうした環境変化の大きい市場において、・・・・・
- <コラム>生保営業職の定着改善、進む!
- ◆従来、生命保険会社の営業職は、職場や家庭を訪問し保険契約の獲得を主たる業務として、女性が多く、「大量採用・大量退職」を前提とした定着の厳しい職場であり職種と言われてきた。しかし、近年の人手不足の深刻化により、大量離職を前提とした人事諸制度の見直しが進みつつある。日本生命など主要8社の営業職の在籍率を調査したところ、入社から1年後(13か月目)の在籍率は平均71%。コロナ禍が流行する以前の19年度と比べて8ポイント高まっていた。5年目は25%だったと言う。本社に勤務する内勤職などと比べると依然として低い水準にあるものの、・・・・・
- <today's>毎年7% 賃上げ ワタミが実施へ
- ◆ワタミは12日、2026年から毎年賃上げを実施する方針を明らかにした。国内の正社員約1200人が対象で賃上げ率は基本給を底上げするベースアップ(べア)や定期昇給を含めて平均7%。積極的な賃上げを打ち出すことで人材確保につなげる。ワタミの渡辺会長兼社長が12日に都内で開いた25年4〜9月決算説明会で明らかにした。同社は今年春季労使交渉で平均5%の賃上げを実施。賃上げは2年連続。長期間にわたる賃上げを続けることで社員の待遇を改善させる。渡辺氏は「インフレに追いつくような賃上げをしていきたい」と話した。・・・・・・・
- <today's>上期介護離職防止へ 一時金 東京海上日動が20万円
- ◆東京海上日動火災保険は介護が必要と認定された親族を持つ社員に、ケアサービスなどの費用として20万円を支給する。早期の介護支援を促し、仕事との両立に悩む社員の離職を防ぐ。企業が介護に必要な費用を一時金として社員に支給するは珍しい。管理職にあたる中高年が仕事と介護の両立に直面していることが背景にある。両立が難しくなれば生産性の低下や離職につながる。経済産業省は2030年時点で介護をしならが仕事をする人が約318万人に上り、経済損失は約9兆円になると試算する。・・・・・
≪連載 第23回≫ 待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 Vol.278
Chapter 3 DX時代の開発手法 10.RPAで人の作業をデジタル化する これまでビジネスプロセスのデジタル化を解説してきましたが、人が行っている作業をそのままデジタル化することもできます。デジタライゼーションの選択肢の一つとして、RPAも検討しましょう。 1)RPAはシステムをつなげる パッチワークのイメージ 働き改革に伴う業務自動化の推進により、RPA(Robotic Process Automation)を導入する企業も増えてきました。デジタライゼーションを行う上で、RPAは業務システム同士をつなぐパッチワークのように活用できます。これにより大きな開発を行わず業務の効率化が実現できます。ここまではSaaSの利用を推奨してきましたが、「SaaSの画面を操作する」と言う業務が新たに発生します。・・・・・
- <コラム>サービス業、人件費増を価格転嫁できず!
- ◆2024年頃から消費者物価は大きく上昇し始め今日に至っている。これに併せ、新卒初任給の引上げを始め給与改善は進んでいるが、如何せん消費者物価の上昇を越えられず実質的に給与は目減りしている状況だ。こうした中、給与アップを図ることも含めて販売価格の転嫁が進んでいるが、価格転嫁には業種によりばらつきがあるようだ。日本経済新聞のサービス業調査によると、2025年度に主要なサービスの料金を上げると答えた企業は2割にとどまる。値上げ意向が6割に達する外食や小売業と比べて低い。労働集約型で人件費増の影響は大きいが、客離れなどを恐れて価格に上手く反映できていないようだ。・・・・・
- <today's>育休カバーで最大10万円 大手金融の支給広がる 三菱UFJが「同僚手当」
- ◆三菱UFJフィナンシャル・グループは2026年春にも、男女を問わず連続1か月以上の育児休暇を取得した社員の同僚に最大10万円を支給する制度を始める。例えば、2人で業務をカバーした場合、5万円ずつ「御礼金」を支給する。育休取得者の代わりに職場を支える人に報いることで、育休が当たり前の職場づくりつなげる。≪中略≫対象者は従業員計約3万8000人。育休者は年間2000人に上る。チームごとに10万円を支給し、誰に分配するかは拠点長が決める。育休取得者は対象外になる。一カ月以上の育休を取得するハードルを下げる狙いがある。・・・・・・・
- <today's>上期倒産、12年ぶり高水準 今年度5172件 人手不足理由が最多
- ◆東京商工リサーチが8日発表した2025年度上半期(4〜9月)の企業倒産件数(負債額1000万円以上)は前年同期比2%増の5172件だった。上半期として12年ぶりの高水準となった。中小企業の人手不足が深刻で、倒産の増加につながっている。内訳をみると、小規模企業の倒産が目立った。従業員10人未満の倒産が4640件と全体の9割を占めた。負債総額は50%減の6927億円だった。人手不足を理由とした倒産は、202件と過去最多を記録した。前年同期(151件)に比べ34%増えた。賃上げ圧力が続き、人件費を価格に反映しにくく中小企業の経営を圧迫している。帝国データバンクによると、企業がコスト上昇をどれほど販売価格に上乗せできたかを示す「価格転嫁率」は25年に39%に下がり、・・・・・
≪連載 第22回≫ 待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 Vol.277
Chapter 3 DX時代の開発手法 8.デジタライゼーションを素早く始める ここではデジタライゼーションを素早く行い、スピーディに結果を出すための開発方法を考えます。 1)素早いリリースが不可欠 業務システムは、完璧なものを作らないといけないというイメージがあるかもしれませんが、ユーザビリティーの視点からは、完璧さはデメリットになる可能性があります。理由は、リリース後に修正を行うのが通常で、リリース時に完成度を高めれば高めるほど、修正コストがかさみます。そのため、完璧さは求めず、ある程度のクオリティで素早くリリースすることを目指しましょう。そうすることでユーザーの声も反映でき、結果としてより良いシステムに仕上がります。・・・・・
- <コラム>最低賃金、全国平均1,121円 上げ幅「目安」上回る!
- ◆先月4日、厚労省の中央最低賃金審議会が2025年度の最低賃金の「目安」を前年実績から63円引き上げ、平均1,118円と決定した。これを受けて、都道府県ごとに決定した2025年度の最低賃金の全国加重平均額は過去最高の時給1,121円となった。現在の加重平均額1,055円から66円増え、過去最大の引上げと額となり、上げ幅「目安」を39道府県が上回った。 今回の改定で初めて47都道府県全てで1,000円を超えた。東京の1,226円を最高に、高知、宮崎、沖縄が1,023円と最も低くなった。最大の引き上げ幅となったのは熊本で、国の目安の64円に18円上乗せし82円の引上げとなった。最高額に対する最低額の割合は83.4%と11年連続で改善した。・・・・・
- <today's>通信制高校 生徒30万人超 今年度最多更新 不登校増加 背景に
- ◆通信制高校に通う生徒が2025年度に初めて30万人を超え、過去最高を更新したことが文部科学省の調査で分かった。不登校の広がりなどが背景にある。学校の新設が相次ぐ中、不適切な運営が指摘された事例もあり、学びの本質の担保が課題となっている。同省が27日に公表した学校基本調査(速報値)によると、通信制高校の生徒数は前年度比5%増の30万5521人。過去5年で1.5倍に増えた。全国の高校生に占める割合は同0.5ポイント増の9.6%だった。通信制高校は戦後、青年らが働きながら学べる学校として設置され、社会人や主婦の学び直しの場にもなってきた。・・・・・・・
- <today's>早期退職 はや昨年超え 1万人超 管理職年代削減で 8月末時点
- ◆日本の上場企業で人員削減が進んでいる。2025年の早期退職の募集人数は足元で1万人を超え、24年通期を早くも上回った。社数は前年より少ないが、製造業を中心に管理職年代の大規模な削減が目立つ。トランプ関税など事業環境の変化や人工知能(AI)時代を見据え、海外で先行する構造改革の動きが日本でも広がってきた。東京商工リサーチによると、25年8月末までに募集が明らかになった国内上場企業の早期・希望退職者数は31社で計1万108人だった。24年は通期で1万9人だった。社数は前年同期より2割以上少ないが、人数は約4割も多い。パナソニックホールディングスが5000人、ジャパン・・・・・
≪連載 第21回≫ 待ったなし!中小企業のDX化のスキームと進め方 Vol.276
Chapter 3 DX時代の開発手法 7.データを正しく取得するための設計 ユーザーの課題を解決するシステムの仕様書が完成しましたので、ここからは、この開発でデータまわりをどのように設計していけば、この先DXでデータ活用ができるかのポイントを見ていきます。1)データを野放しにしない デジタライゼーションの目的は、ブラックボックス化していたレガシーシステムを新しい業務システムに更新してデータを集約することです。この時注意しなければならないことは、個々人の業務PC に保存されているデータがあるということです。例えば、マーケッターがデータを分析するにあたり、Excelを使っていたとしたら、そのデータはマーケッターの個人の業務PCにしか存在・・・・・
- <コラム>25年度 最低賃金の目安 1,118円!
- ◆2025年度の最低賃金を巡る議論が8月4日の会議で決着した。背景には、「2020年代に1,500円」との目標実現にこだわる政府の意向があったが、厚労省の中央最低賃金審議会は経済データに基づき「6.0%」を引上げ率の上限とした。 目安額の全国加重平均は、24年実績から63円引き上げて、1,118円となった。目安通りに引上げが実施されると、すべての都道府県で最低賃金は1,000円を超える。最低賃金は、企業が従業員に支払わなければならない最低限の賃金で、正社員やパート、派遣社員などに関わらず、・・・・・
- <today's>男性の育休、初の取得4割 昨年度、10ポイント増 中小は伸び悩み
- ◆厚生労働省は30日、男性の育児休業取得率が2024年度に40.5%になったと発表した。前年度を10.4ポイント上回り、過去最高を更新した。企業による意向確認や取得状況の公表などが義務付けられたことが奏功した。大企業に比べ中小企業の伸び悩みも見られた。24年度の雇用均等等基本調査で、5人以上を雇用する事業所を調べた。男性育休の取得率は22年10月から23年9月の間に配偶者が出産した男性の内、24年10月1日までに育休の取得または申請した人の割合を指す。女性の育休取得率は86.6%だった。事業所の規模別に男性の取得率を見ると、500人以上では前年度比19.6ポイント上昇の53.8%と大きく伸びた。・・・・・・・
- <today's>日本人の減少 過去最大90万人 外国人11%増、労働力依存
- ◆総務省は6日、住民基本台帳に基づく人口を発表した。1月1日時点の日本人は1億2065万3227人で前年から90万8574人減った。16年連続のマイナスで、前年比の減少幅は調査を始めた1968年以来、最大となった。 日本人人口はピークだった2009年から642万2956人減った。少子高齢化の進展により死亡数が出生数を上回る「自然減」が拡大した。死亡者数は159万9850人と過去最高で、出生者数の68万7689人は最も少ない。外国人は11%増えて367万7463人となり、初めて350万人を超えた。増加幅も過去最大の35万4089人だった。・・・・・